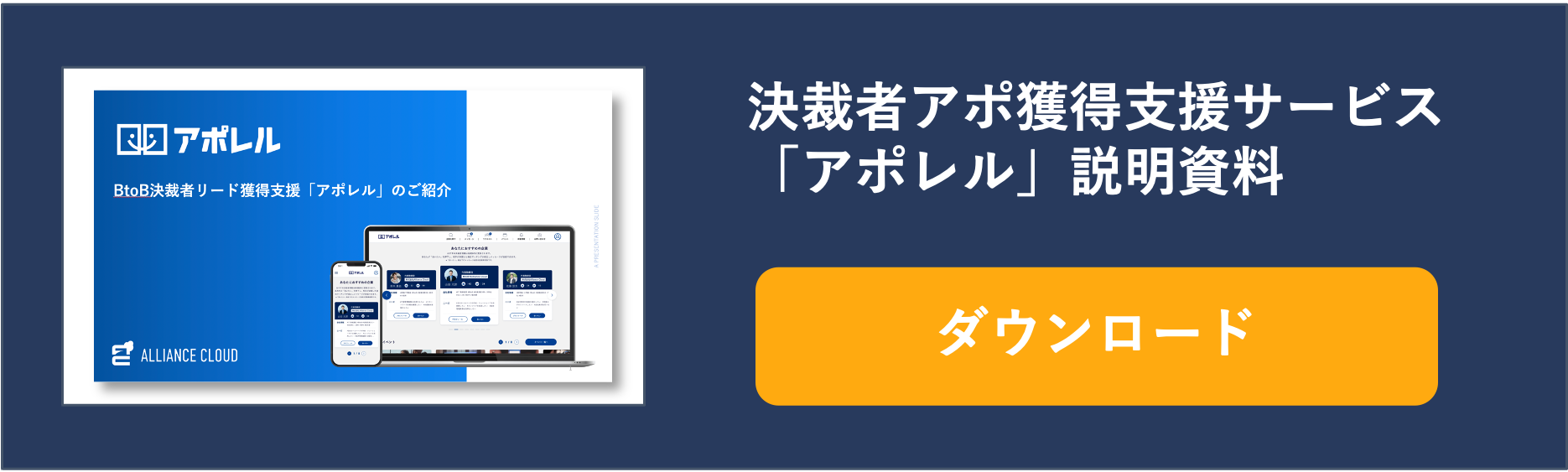米田 光宏(よねだ・みつひろ)
株式会社ツナググループ・ホールディングス 代表取締役社長
1969年大阪府生まれ。関西学院大学経済学部卒業後、株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルート)入社。 主にマーケティングや商品開発、組織コンサルティング業務を担当する。2007年株式会社ツナグ・ソリューションズを設立し、同社代表取締役社長に就任。2019年4月、株式会社ツナググループ・ホールディングスに商号変更。著書に「Tsuna・Good!社員が走りたくなる8つのシカケ(2010年12月)/クロスメディア・パブリッシング」。

日本のサービス産業は、アルバートやパートの労働力に支えられています。必要な人員を確保できないと、経営そのものが立ち行きません。コロナ禍の影響で採用のスタイルが大きく様変わりするなか、企業と求職者をつなぐ新しいシステムとはどのようなものなのか。アルバイトやパートに特化した採用支援コンサルティングの先駆けである株式会社ツナググループ・ホールディングスの米田様にお話を伺いました。
採用満足度にコミットした支援を目指す

--本日はよろしくお願いします。早速ですが、米田さんの起業までのプロフィールをお聞かせください。
1993年に関西学院大学経済学部卒業後、アルバイトやパートの求人広告メディアを手がける株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルート)に入社し、営業や事業企画を担当していました。
1993年はちょうどバブル崩壊の直後で、終身雇用、年功序列型の賃金体制といった日本的経営の見直しが始まり、人材の流動化がますます進むと考えられていました。また、2010年には人口がピークアウトして、少子高齢化がさらに加速すると予想されていたこともあり、「ホワイトカラー×正社員」ではなく、より多種多様な働き方が広がると考えたのです。
--起業を決意されたのはどのような理由からですか。
リクルートは当時も今も求人のナンバーワンメディアなのですが、有効求人倍率が1.0を超えた2006年頃は、サービス業を中心とした大手企業の採用ニーズを100%満たしているとは言えない状況でした。ナンバーワンのメディアとはいえ、網羅できていない地域はもちろん存在します。例えば、郊外の店舗の主婦パートの募集は、チラシメディアの方が優勢だったのです。
そこで、クライアントサイドに立ち、人材採用を成功させるためのコンサルティングを行う新規事業を2007年に立ち上げ、独立しました。目指したのは、企業のニーズに合わせてポートフォリオを組み、採用の満足度にコミットすることです。
飲食に代表されるサービス業では、「現場の人数×1人当たりの生産性」が売上になりますが、スタッフのモチベーションのレベルによって売上は大きく変わってきます。そのため、シフトを埋められる量と現場スタッフの質を重視しました。
また、採用は通常、決定課金であれ広告課金であれ、ステップごとに費用が必要なのですが、年間を通じて採用の最適化を図ることで、重要な経営課題の人手不足を解消したいと考えました。
3つの柱を軸に時代に即した採用支援事業を展開
--貴社の事業について改めてご説明をお願い致します。
現在、採用支援事業、短期単発支援事業、主婦やシニア層の採用支援事業の3つが当社の事業の柱です。
採用支援事業は、RPO(リクルートメント・プロセス・アウトソーシング)事業と呼んでいます。当社は、アルバイト、パートの採用を専門とするコンサルティング会社ですが、採用支援を行っても現場がうまく回らないことがありました。例えば、飲食業界では店長が採用に時間を取られると、肝心の営業にかける時間が減ってしまいます。
そこで、採用そのものもアウトソーシングで受けようと考えました。ポートフォリオを組んでメディアや派遣会社と交渉して、顧客に人材を供給します。費用は月額固定なので、どれだけの媒体を使っても値段は変わりません。
--短期単発支援事業ではどのような取り組みを展開されていますか。
RPO事業に取り組んでいると、世の中に足りないものが見えてきました。それは短期、単発で働ける人材です。レギュラー人材はRPO事業で獲得できますし、応募への対応などもアウトソーシングにして、業務の効率化を図れます。
しかし、安定した店舗運営の中で必ず出てくるのが「風邪をひいたから休みます」といった欠勤の問題です。また、お店のある地域で大きなイベントがあり、お客様がその日だけ急増する場合なども、募集が追いつきません。いずれもそれほど高頻度ではありませんが、とても困った状況です。
私たちはほぼ全てのメディアとつながっていましたが、このニーズを満たすものはありませんでした。そこで、Yahoo!が運営していたショットワークスに着目して、当社のサービスの1つに加えました。その日1日だけ働く人を集めるためのメディアです。現在では、ショットワークスコンビニやショットワークスデリバリーといった派生商品にもつながり、業界ナンバーワンになりました。
--主婦やシニア層の採用支援事業はどのような背景で生まれてきたのですか。
人手不足で供給側が有利になると、働く人は自分の都合に合った日・時間だけ働きたいなど、より便利な働き方を求めるようになります。特に主婦やシニアに多いのは、できるだけ自宅の近くで働きたいといった要望です。
少子高齢化がますます加速する日本において、必要な労働力を確保するためには、主婦やシニアにリーチすることが非常に大切です。そこで、地域限定のユメックスという折り込み広告の会社を買収し、主婦やシニア層に向けた情報提供ツールを手に入れました。
--人材採用の業界もコロナの影響を強く受けていますか。
この先2030年頃には、人材採用の業界はビフォーコロナ、アフターコロナという考え方が一般化するほど大きく変容していると思います。コロナ以前に新卒採用された人は、企業説明会に行き、一次選考を受け、二次選考以降会社を訪問するという動きを、応募した会社の数だけ行う必要がありました。
しかし、コロナ以降はこうしたプロセスを踏んでいるケースはほとんどありません。広告について言えば、「集めて選ぶ」から「探して選ばれる」へと人材マーケットは確実に変化しました。
広告を打ち、それを見た人を集め、選ぶというのがビフォーコロナでした。アフターコロナでは、企業側から求職者に声をかけて企業が選ばれます。会社ごとに求職者がプロフィールを提出するのではなく、まず求職者がプロフィールを公表して、そのプロフィールを見た企業がアプローチするというスタイルです。アメリカではずっと以前からこうしたレジュメ型の採用が一般化しています。
「協働」で生産性を高めて日本を元気にしたい

--今後の中長期的な事業展望についてお伺いできますか。
アフターコロナの変化に対応すべく進めているのが、オウンドメディアリクルーティングです。
自社のホームページに、採用情報に関する新鮮なコンテンツをしっかりと用意することで、求職者に選ばれること、ペイドメディアリクルーティングからオウンドメディアリクルーティングへの変革を目指します。
ペイドメディアではメディアごとのルールに従って情報が発信されます。一方、ルールの縛りがないオウンドメディアであれば、ペイドメディアでは正確に伝えることができない情報も、多くのテキスト、写真、動画までを使ってしっかり届けることができます。求職者にとってもより正確で有益な情報が入手できるでしょう。
現在のところ、アルバイト、パートの採用でこうした事業に取り組んでいる企業はありません。そこで、当社が先駆けとなり、当社事業の大きな柱に成長させたいと考えています。
--新規事業成長のポイントはどこにありますか。
企業が発信する情報を、いかにして求職者の元へ届けるかというところに我々の手腕がかかっています。
調理師の方を例に取ると、ランチタイム後の14時〜15時は仕込み前の休憩時間で、Yahoo!のスポーツニュースを見ているというペルソナが設定できるでしょう。このようなケースでは、Yahoo!ニュースの14時〜15時の時間帯に広告を打てば、効果が期待できます。
このように、ターゲットにリーチできる手法を我々が開発し、情報発信を行うことで、ペイドメディアではなくオウンドメディアでメッセージを届けることが可能になるのです。
--最後にProfessional Onlineを見ていただいている経営者、決裁者の方に向けてメッセージをいただけますか?
コロナ禍により、ビジネス界全体に関わる大きな問題が露呈したと考えています。それは「低生産性」です。コロナの影響で人の流れが止まった途端に、儲からないという状況が発生してしまいました。とりわけサービス業において顕著で、大きな経営課題になっています。
当社では、これまで「つなぐ・つなげる・つながる」をミッションとして、企業と人をつなぐ事業を展開してきました。これからは、企業と企業、場合によっては人と人とのつながりを生み出し、生産性の向上に寄与していきたいと考えています。
例えば、店舗の掃除をロボットで行うと考えれば、企業とロボットメーカーをつなぐことが仕事になります。店舗のレジ業務を1人で対応できるようにするために最新式のレジを導入するのであれば、レジスターのメーカーと店舗をつなぐことは、その店舗の生産性を高めることにつながります。
従業員は人間にしかできない業務に集中することで、仕事に対するモチベーションが向上し、こちらも生産性が高まるでしょう。企業も人件費以外の固定費に投資することで、生産性が改善され利益につながります。このように、会社の利益を人に還元するようにしていくことで、日本が元気になると信じ、アフターコロナの時代を戦っていきたいと思います。
--つながりが大切ということですね。
「競合」という考え方がありますが、これはマーケットが拡大していた時代の考え方です。マーケットが小さくなっている時にグロスを取っても意味はなく、もはや「競合」している場合ではありません。
当社では、「競合」から「協働」へのシフトを目指し、現場の生産性を高めるためのテクノロジーやアイディアを持っている企業や個人とどんどんつながっていきたいと考えています。当社のお客様はほとんどが大手なので、テクノロジーの導入によって、生産性のより大きな向上が期待できます。
例えば、技術系のスタートアップベンチャーと大手企業をつなげることで、大手企業は生産性を大幅に向上でき、ベンチャー企業はさらなる成長を目指すことができます。
これから共に「協働」文化を日本に根付かせ、1+1を2で終わらせるのではなく、3にも4にもしていきましょう。
--本日はありがとうございました。
株式会社ツナググループ・ホールディングス
Professional Onlineでは無料で経営者インタビューに掲載いただける方を募集しています。
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
プロフィール

米田 光宏
会社情報

決裁者アポ獲得支援サービス「アポレル」に登録すると、日替わりでレコメンドされる著名な経営者と出会うことができます