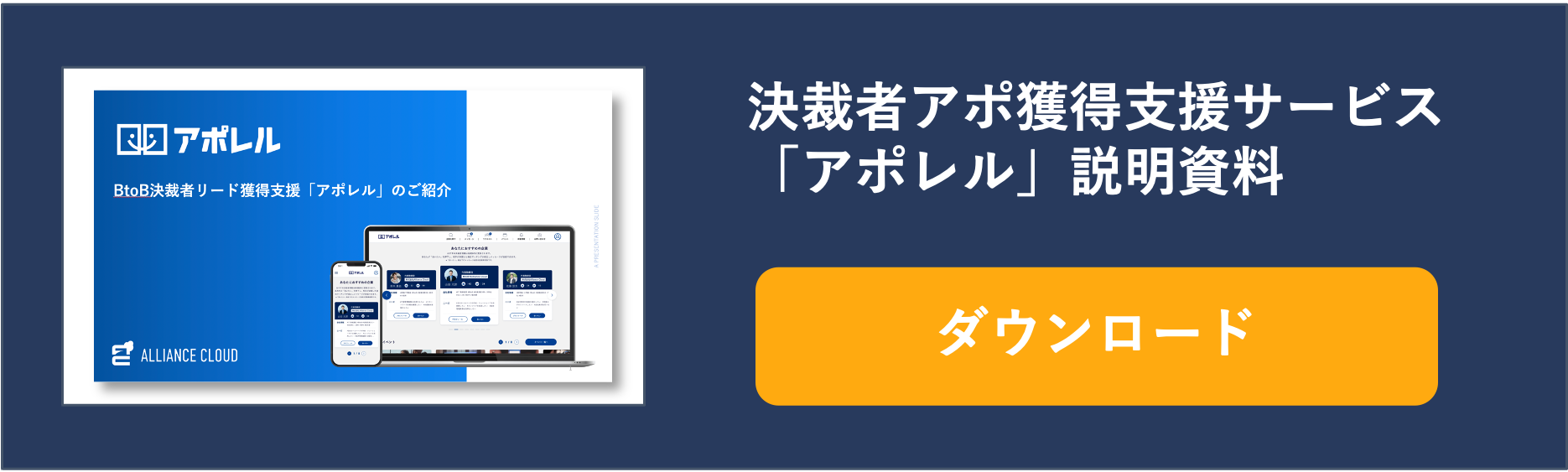濱田 金男(はまだ・かねお)
合同会社 高崎ものづくり技術研究所 代表
長野工業高等専門学校を卒業後、沖電気工業に入社し、30年ほど勤務する。2013年に中小企業に転職、技術者として働き、2014年に独立。現在の会社を立ち上げ。個人での活動を開始する。今までの実務経験を活かし、社内研修や社外のセミナー、製造業の新製品製造立上げ支援を行う。

自身のこれまでの経験と知識を基に、それぞれのケースに適した品質管理技法を開発、提供し、実績を築いてきた合同会社 高崎ものづくり技術研究所。コロナ禍の影響で従来のface-to-faceでの支援が難しくなってきており、新たな媒体などを活用することを模索されています。今回は合同会社 高崎ものづくり研究所代表の濱田様にお話を伺いました。
技術・知識・経験の蓄積からクライアントの悩みの解決やアイデアの提案を
--本日はよろしくお願いします。早速ですが、濱田さんのご経歴についてお聞かせください。
長野工業高等専門学校を卒業後、沖電気工業に入社し、35年間勤務しました。沖電気工業では、主にプロジェクトリーダーとして機械装置の電子回路設計や、システム設計に従事していました。
また、在職中に中国での新規工場の立ち上げプロジェクトメンバーに抜擢され、品質管理部長として参画し、製造工程の品質管理方式企画立案に従事しました。中国の事業所では、ISO9000品質システムの構築、社内作業者向け品質管理教育、現地協力工場品質管理、品質管理教育訓練の実施などの業務に従事していました。
その後、中国の別会社に移り、品質保証部長としてISO9000品質システム構築、社内改善活動の立上げ、作業者や検査員に対する品質管理や、検査員教育訓練の業務に従事しました。
そして日本に戻り、2007年に地元の中小企業に入社したのですが、中国で新製品の委託生産業務に従事することが決まり、再び中国に渡りました。そこでも業務先委託協力工場の製造工程の改善、従業員に対する品質管理や、不良解析手法などの教育訓練の実施に努めました。
2014年からは会社に所属することをやめ、自身で現在の「合同会社 高崎ものづくり技術研究所」を立ち上げ、個人での活動を始めました。高崎ものづくり技術研究所では、自身のこれまでの経験を活かし、製造業の製造工程品質改善、設計工程改善の支援業務などに従事しています。
その他にも東京や大阪、群馬でセミナーを主催してきました。セミナーの内容としては、工場の品質管理手法、FEMA/FTA、QC改善活動についてなどになります。ですが、近年のコロナの流行の影響によりセミナーの開催や、主として取り組んでいたface-to-faceのコミュニケーションが困難になってきていますので、別の有効な方法を模索しなくてはと考えています。
中小企業を盛り上げ、日本の得意技術を継承発展させる!
--現在行われている事業展開につきまして、改めてご説明をお願い致します。
当社の主な業務としては、メルマガやメール講座を無料で定期的に配布しています。さらに、製造業の現場ですぐに使える改善手法マニュアルや動画をオンラインで提供しています。その他ですと、新製品の立ち上げや委託生産のお手伝いなどもしています。
コロナが流行するまではオープンセミナーや、企業に直接伺い、現場改善、セミナーや研修会なども行っていましたが、現在は需要が下火になってきています。
--現在何名ほどのクライアントがいらっしゃるのでしょうか。
ホームページからのお問い合わせや、マニュアルの配布などでお客様のメールアドレスが集まりますので、その方たちを見込み客とすれば現在4,000人程度おられます。その方たちに対して、定期的にメルマガを配信することで依頼に繋がるケースが多いです。
--クライアントとなる方の層や課題について教えていただけますか。
お客様の層としては、中間の管理職、第一線の技術者や監督者の方が多く、数は少ないですが経営者の方も一定数おられます。
製造業における課題は、人が関わっていることにより起こるトラブルや製品の不良と、会社全体の業務の流れの問題による生産性低下や、管理システムの問題の大きく2つに分けられます。
人がかかわる問題の場合は、同じ問題が何度も起こる、生産性が上がらないなどがあり、こういった場合には、IOT化、デジタル化などの改善提案を行います。
業務フローや管理システムの問題の場合は、全体最適の観点から、品質向上、生産性向上のための仕組み化提案が必要となります。
このような課題を解決するための手順や手法をマニュアルやメルマガ、YouTubeを通して提供したり、直接ご指導させて頂いている形となります。
--クライアントの規模感に特徴はありますか。
20〜30人程度の小規模な会社から数百人程度の中規模な会社、大企業であってもセクションや部門単位になるので数百人単位であることがほとんどです。なぜなら、ご提案する際は最初に、その部署・部門・工場の品質改善、生産性改善から始めるためです。
--昨今の状況を踏まえると、実際の現場で働く人も変化してきているのでしょうか。
そうですね。非正規の人や海外の労働者の方の数が増えてきています。また、働き方改革の影響もあって、条件的に厳しくなることが増えてきており、仕事が進めにくくなってきているというのはあります。若い方も増えてきておりますので、インセンティブの導入なども案として提案することが増えています。
--貴社のように中小企業をターゲットとして支援を行っている企業はどの程度おられるのでしょうか。
数としてはかなり存在しますが、中小企業をターゲットとするのは非常に難しいと考えています。理由としては、中々お金に結び付かないということがあります。ですが、日本の製造業にとって、中小企業はとても重要な役割を果たしていると考えていますので、なくてはならない事業として取り組んでおります。
--貴社の独自性や強みについてお伺いできるでしょうか。
製造業の豊富な経験を基に、すぐに使える人材育成や業務改善手法の提案ができるということが、強みや独自性に繋がるのではと考えています。
弊社では、製造業の仕事のやり方を具体的に整理してまとめたマニュアルや、DVDをシリーズ化して提供しています。時代に合った考え方に変革し、独自の商品やサービスにつなげるヒント、新しい技術開発のためのヒントなど具体性のあるものを提供できるということが強みになるのではと考えています。
具体的には、品質管理の基本、ヒューマンエラー対策、現場改善・生産現場改革の進め方、独自製造技術、商品の開発設計、FMEA実施手順などの実践的ノウハウの提供が可能です。
時代に合わせたサービス事業の構築を
--今後の中長期的な事業展望についてお聞きできますか。
これまではセミナーの開催や、実際にクライアントを訪問するというface-to-faceの形で事業に取り組んでいました。
しかし、現在のコロナ禍の状況では中々難しくなってきています。弊社は以前から現場で使用できるようなマニュアル、動画などを作成したり、メールマガジンの発信などを行ったりしていました。
今後はこういった教育関連の媒体の作成により一層力を入れ、情報発信などの形での展開を視野に入れています。
--最後にProfessional Onlineを見ていただいている経営者、決裁者の方に向けてメッセージをいただけますか?
日本の中小企業の技術力は世界的に見ても高い水準にあり、知識も豊富です。人を活かす形で中小企業を活性化していかなくては、技術力が海外に流れてしまい、日本の技術は沈滞してしまいます。
日本の製造業の中で中小企業が占める割合は非常に大きいです。かつての日本のような賑わいをみせることは難しいでしょうが、なんとかして盛り上げていければと思い、私自身も日々模索しつつ、活動を続けています。
また、現在の状況ではお客様との関わり方やサービスの提供の仕方も時代に合わせていく必要があると考えています。
品質改善や業務改善、従業員の教育などにお悩みのことがあれば、お気軽にご相談ください。
--本日はありがとうございました。
合同会社高崎ものづくり合同研究所
https://monozukuri-takasaki.com/
Professional Onlineでは無料で経営者インタビューに掲載いただける方を募集しています。
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
プロフィール

濱田 金男
会社情報


決裁者アポ獲得支援サービス「アポレル」に登録すると、日替わりでレコメンドされる著名な経営者と出会うことができます