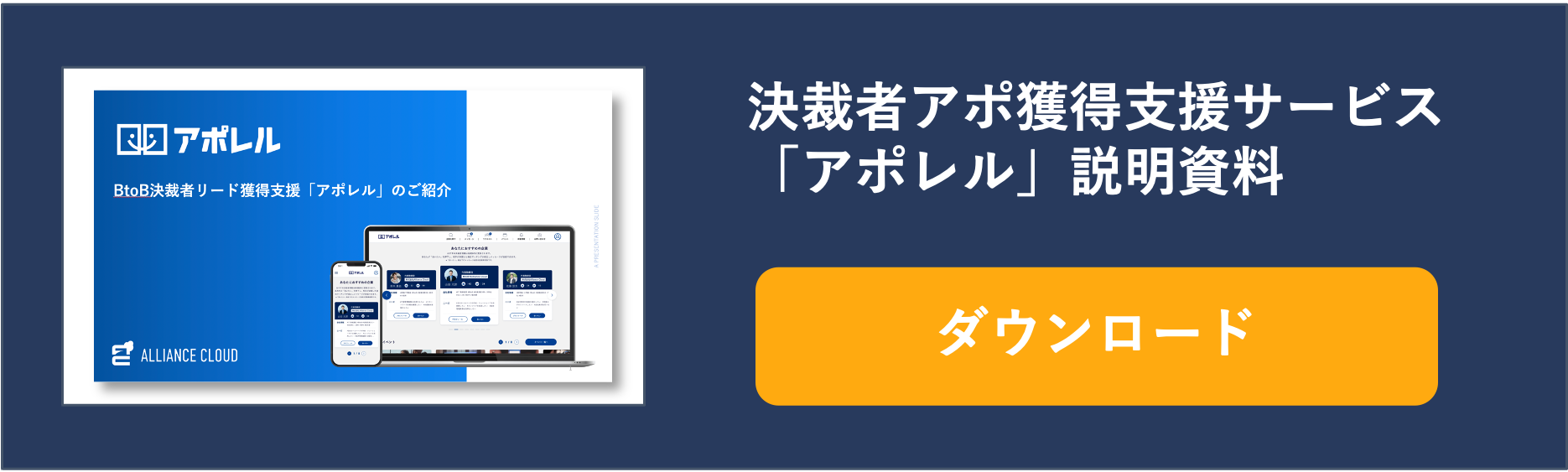契約書を作成する前に!営業代行とは?
業種を問わず、ビジネスを展開していく上では営業活動は欠かすことができません。BtoCであってもBtoBであっても、自社の製品やサービスを必要としている人の元へ届けるためには、営業での売り込みが大切です。
しかし、起業したてのスタートアップ企業や事業規模を大きく展開したい企業などは、営業スタッフの育成が追いつかないことも少なくありません。そのような場合に、営業代行の利用がおすすめです。
営業代行を利用するときには、必ず契約書を作成します。契約書には必ず盛り込まなければいけないポイントがいくつかあります。契約書に不備があったために、営業代行会社や営業代行スタッフとのトラブルになることもあります。そのようなトラブルを事前に防ぐためにも、不備のない契約書の作成は欠かせません。
この記事では、営業代行とはどのようなもので、契約書に欠かせないポイントとはどのようなポイントなのか詳しく解説します。
営業代行について
営業代行とは、言葉通り営業を代行して行ってくれるサービスのことです。営業代行を請け負う企業には、多くの現場で営業経験を積んできたプロの営業スタッフが多く在籍しています。
本来であれば、それぞれの会社が自社で営業スタッフを育てて戦力にするのが一番ですが、創業したての規模の小さな会社など、営業スタッフを育てている余裕も、正社員として優秀な営業スタッフを雇う余裕もない会社も少なくありません。
営業代行なら、必要なときに必要なスキルを持った必要な人数をすぐに揃えることができるので、どのような商品やサービスであっても営業の業務委託ができるのです。
>>【無料】営業代行サービスの比較検討をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
営業代行を依頼する時の流れ
営業代行を利用することを決めたら、どのような流れで契約まで進めればいいのでしょうか。営業代行の流れは次のように契約まで進みます。
1.営業代行会社へ問い合わせ
まずは営業代行会社を見つけて問い合わせをします。Webなどで「地域名 営業代行」などと検索すると、その地域で営業活動を行っている営業代行が見つかります。営業代行と一口に言っても、訪問、テレアポ、顧客発掘など、会社によって得意分野が違います。自社のニーズを満たせる営業代行会社を見つけることが大切です。
問い合わせたらおおよその見積もりを取ります。必ず1社だけでなく、複数社から見積もりを取り費用だけでなく条件などもよく検討しましょう。
2.打ち合わせ
営業代行を依頼する候補を絞ったら打ち合わせを行います。販売する商品やサービスの内容に関する詳細や売上目標を伝えて、営業代行会社から提案を受けて、営業戦略プランを練ります。このときに、営業に入る代行会社のスタッフとの顔合わせを行うこともあります。
3.契約締結・業務開始
営業代行会社からの提案内容や打ち合わせで練り上げた戦略プランに問題がなければ契約締結へと進み、実際の業務へと入ります。業務が始まったら定期報告を受けられるので、必要に応じてその都度、営業戦略の見直しを行っていきます。
営業代行の契約書の作成は似ている言葉との違いを理解しよう!
営業代行の契約書を作成するときには、細かい言葉に気をつけなければいけません。契約書に記載される言葉の使い方によって、業務委託内容や報酬の支払い方に対する解釈が変わってきてしまう可能性もあります。
特に契約書の作成の際に間違えやすいのが、「代行」と似たような言葉の「代理」「委託」「派遣」との違いです。「代行」とこの3つの言葉の違いについて解説します。
代理について
代理とは本人に変わって法律的な行為を行うことです。民事裁判で弁護士のことを「弁護人」ではなく「代理人」と呼ぶのは、本人から委託を受けて法律的な裁判の手続きや交渉を行うためです。代理人になれるのは、弁護士以外では本人に対して親権を持つ親など、一定の関係を持つ人だけです。
代行では法律的な行為に該当しない活動を、本人の代わりに行うものです。営業活動は法的な行為ではないので、「営業代理」とは呼ばずに「営業代行」になります。
委託について
業務を誰かの代わりに行う仕事を指す「代行」という言葉は、実は法律上は正式な契約用語ではありません。業務代行の契約を結ぶためには、代行を依頼する会社と代行会社の間で業務委託契約を締結しなければいけません。
営業代行とは「営業活動を代行する行為」であり、そのために結ぶ業務委託契約は「営業業務を代行するために必要な契約形態」となります。
派遣について
別の会社のスタッフに自社の業務を依頼する形式には「派遣」という契約方法もあります。派遣と業務委託の違いについての理解も大切です。
派遣と業務委託の違いとは、指揮命令権がどこにあるのかという違いです。派遣の場合には、派遣されたスタッフに対する指揮命令権は派遣先の企業にあります。派遣スタッフは派遣先の企業の責任者の指示のもとで業務を行います。
一方の業務委託は代行会社に指揮命令権があります。スタッフは代行会社が定めた計画に基づいて業務を行います。そのために、業務開始前に代行会社との綿密な打ち合わせを行い、詳細な戦略プランを練っておく必要があるのです。
営業代行の場合には、人的リソースのみが必要で自社の管理のもとで営業スタッフに働いてもらった方がいい場合に派遣がいいでしょう。スタッフのマネジメントや営業ノウハウも必要であれば代行会社への委託がおすすめです。
営業代行の契約書は雇用契約書なの?
営業代行を依頼するときの契約書の種類は、雇用契約書なのかどうか気になっている企業の担当者の方もいるようです。営業代行を依頼するときの契約書は雇用契約書なのかどうか解説します。
雇用契約書について
雇用契約書とはどういったものなのか見ておきましょう。雇用契約書とは、労働契約書とも呼ばれるもので、雇用主(会社側)と働く労働者の間で労働条件を明らかにするために交わす契約書です。
雇用契約書には、勤務時間や給与、休日等の労働条件について細かく記載されていて、雇用主と労働者の間で確認して同意した上で、両者が署名捺印して保管します。
雇用契約書は雇用形態の種類に限らず必要です。正社員だけでなく、アルバイトやパートといった雇用形態の種類であっても、必ず雇主と労働者の間でかわさなければいけません。
口頭での雇用契約も可能ですが、労働条件について、言った、言わない、といった争いになりがちなので、両者が署名捺印した上で書面として残すことが法的には求められています。
営業代行で使うのは業務委託契約書
営業代行を契約する場合には、代行会社から派遣されてくる営業スタッフと派遣先の会社で雇用契約書を交わすわけではありません。営業代行を代行会社へ依頼するときには、営業代行会社への業務委託契約となります。
そのために、営業代行で交わす契約書の種類は業務委託契約書になります。雇用契約書と業務委託契約書の違いとは、契約を交わす2者の間に従属関係があるかどうかです。
雇用契約書の場合には、雇用主と労働者の間に従属関係が生じ、雇用主からの命令や指示に従う義務が労働者に生じます。業務委託契約書の場合には、委託された相手が一定の成果を出したら報酬を支払います。業務を行うのに、依頼主の指揮命令下に入る必要はありません。
個人で営業代行を請け負っている人もいますが、個人の営業代行であっても独立した事業者です。業務委託であれば、依頼主と営業代行は事業者同士の契約を結ぶということになります。
営業代行の契約書の種類
営業代行で交わす契約書は業務委託契約書ですが、事業者間で業務委託に関して交わす契約書の種類には業務委託契約書の他に、請負契約書、準委任契約書があります。それぞれの違いについて理解しておきましょう。
業務委託契約の特徴
営業代行で結ぶ契約書の種類である業務委託契約書とは、業務の内容や金額について業務を依頼する会社と、業務を依頼される会社や個人事業者との間で締結する契約書です。業務委託契約書に記載される内容とは次のような内容です。
- 業務内容
- 契約金額
- 納期
営業代行で営業活動を行うスタッフと、依頼した会社との間には雇用関係はなく、営業スタッフは営業代行会社の指揮系統のもとで業務を行います。また、労務管理の責任も営業代行会社にあります。
よくあるトラブルは、業務委託で派遣されているスタッフに対して、自社のスタッフと同じように依頼主の会社側が残業や休日出勤などを命じてしまうような例です。営業代行会社のスタッフに訴えられてしまうと、依頼主の会社に責任が生じてしまいます。業務委託契約のスタッフは自社の指揮命令下には無いことをよく理解しておきましょう。
基本的に、業務委託契約では依頼主に進捗の報告義務はありません。進捗の報告を希望する場合には、業務委託契約書への記載が必要です。
請負契約の特徴
業務委託契約書とよく似た契約書の種類に請負契約書があります。請負契約書とは、依頼主が報酬を支払う対象が成果物であるという契約書です。建設関連やITシステム構築、ソフトウェア開発、Webサイト制作などでは通常は請負契約が結ばれます。
成果物への完成責任は依頼主ではなく請け負った側にあります。納品後であっても、成果物に不具合があった場合には、請け負った会社が対応する義務を負います。
準委任契約の特徴
業務委託契約書とよく似た契約書の種類に、準委任契約書もあります。準委任契約書に似た種類には委任契約書がありますが、委任契約書は法律行為を委任する場合の契約書の種類です。委任契約書は通常は弁護士、税理士、会計士などに業務を委任する場合に交わします。
準委任契約書は法律行為ではない事実行為を委任する契約書の種類です。業務や行為の遂行に対して報酬の支払いが発生します。コンサルティングやシステムエンジニアへの業務依頼で通常はかわされる種類の契約書です。
準委任契約書の特徴は、納期までに成果物が完成しなくても、契約上の責任を果たしたとみなされる点です。納品物に不具合があっても委託された側には責任はありません。
ただし、業務・行為に対しての責任は負います。契約したのに契約期間中に仕事をしなかった場合には債務不履行になります。
営業代行の契約書の記載内容
営業代行を依頼したら交わす業務委託契約書にはどのような内容を記載したらいいのでしょうか。契約書へ記載するべき内容について解説します。
欠かせない項目
営業代行の業務委託契約書に記載する内容に、法律で決められている記載内容はありません。しかし、必要事項の記載に漏れがあると、後で問題が発生したときに記載漏れが原因でトラブルになる可能性もあります。そのために、必要事項を細かく記載する必要があります。営業代行の契約書に必ず記載するべき内容は次のような記載事項です。
- タイトル
- 契約の目的
- 委託する業務内容
- 権利義務の帰属先
- 委託業務の遂行方法
- 報酬と支払時期
- 諸経費
- 損害賠償
- 営業代行の実施報告
最も大切なのは業務内容と報酬についてです。営業と一口に言っても、業務内容を分解すると多くの業務があります。報酬の発生がどのタイミングになるのか、契約書へ具体的な記載が必要です。
「テレアポ」といっても、電話をかけた本数に対する報酬なのか、アポを取ればいいのか、交渉成立が報酬発生のタイミングなのか、会社によって考え方が違います。契約書に具体的に記載しておかないと、後から報酬を払う、払わない、といったトラブルに発展してしまいます。
業務内容と報酬の発生のタイミングはできる限り細かく契約書へ記載するようにしましょう。
雛形はダウンロードできる
営業代行の契約書を自分でゼロから作成しなければいけない場合でも、インターネット上には無料でダウンロードできる雛形がいくつかあります。WordやExcel形式でダウンロードできる雛形のファイルもあるので、お使いのPCで開いてすぐに記載できます。
Webで「営業代行 契約書 雛形」と検索してみましょう。すると、検索結果にダウンロードできる雛形が表示されます。記載しやすく使いやすい雛形を見つけて、契約書の作成に役立ててみましょう。
営業代行の契約書を作成する時の印紙の必要性
営業代行の契約書を作成するときに、収入印紙の貼付が必要かどうか悩む方も多いようです。収入印紙とは、印紙税法で契約書や金融証券などの特定の文書への収入印紙の貼付によって納税することを義務付けられているものです。
営業代行の契約書は印紙税法の請負契約の契約書である第2号文書に当たるので、印紙税が発生します。しかし、印紙税が発生しない営業代行の契約書も存在します。収入印紙の貼付が必要ない場合と、収入印紙の貼付が必要な場合について解説します。
印紙が不要なケース
収入印紙の貼付が不要な営業代行の契約書とは、業務委託契約書に記載される契約額が1万円以下の場合です。1万円以下の契約書では、印紙税が免除されます。
印紙が必要なケース
しかし、営業代行の契約金額が1万円以下ということはまず考えにくいので、基本的に収入印紙の貼付は必要だと考えましょう。必要な収入印紙の金額は、契約書に記載される金額によって次のようになります。
| 契約書に記載される金額 | 収入印紙の額 |
| 1万円以上~100万円以下 | 200円 |
| 100万円超~200万円以下 | 400円 |
| 200万円超~300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超~500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超~5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超~10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超~50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超~ | 60万円 |
| 契約金額の記載がない場合 | 200円 |
営業代行の契約書の注意ポイント
営業代行の契約書を作成するときには、いくつか注意しなければいけないポイントがあります。業務委託で、万が一トラブルが発生したときには、契約書に記載されている内容が、トラブルの責任の所在がどこにあるのかを確認するための重要な手段となります。無用なトラブルを回避するためにも、営業代行の契約書を作成するときに、特に注意するべき点について解説します。
依頼内容を明確にする
一口で営業代行と言っても、営業の業務は大きな幅があります。市場調査から依頼するのか、電話を掛ける先のリストの作成も依頼するのか、テレアポでアポイントメントが取れたらその後の商談はどうするのか、既存顧客のフォローも代行に依頼するのか、依頼主と営業代行会社で認識を完全に一致させておかなければいけないので、記載内容には注意が必要です。
業務内容に関する両者の認識に齟齬がある場合、依頼主としては「報酬を支払っただけの成果が得られなかった」ということになりかねません。依頼したい営業業務を細かく分解した上で、営業代行会社に依頼する業務内容と、自社のスタッフが行う業務内容について、契約書へ記載するように注意しましょう。
経費の分担を明確にする
営業活動を行う上では、通信費や交通費、交際費と言った諸経費が発生します。経費を報酬に含めるのか、実費を依頼主が支払うのかについても、契約書へ明記するように注意しましょう。
営業代行では依頼主の多くが、報酬と成果にだけ目が向いてしまい、経費へ注意が向きません。意外に経費が高額なることに後から気がつく場合もよくあります。また、顧客から損害賠償を訴えられた場合には、その責任が販売した営業代行会社のスタッフにあるのか、依頼主にあるのか、責任の所在も明記しておくように注意しましょう。
進行の把握を明確にする
営業代行を依頼するということは、営業業務を委託するので、営業スタッフは自社の指揮系統下には入りません。営業スタッフは営業代行会社の指揮系統のもとで営業活動を行うという点は要注意ポイントです。
業務委託したからと言って、営業代行会社へすべてを任せてしまうのはとても危険です。万が一、営業が原因で顧客とトラブルが発生したとしても、責任は依頼主が負わなければいけません。そこで、何らかの形で依頼主が営業スタッフを監督できる仕組みが必要です。
定期的な報告を義務付ける、依頼主の企業の担当者と営業スタッフとの定期的な面談を設けるなど、業務の進捗状況を確認して、認識を共有するための仕組みを契約書へ盛り込むように注意しましょう。
納期の取り決めを明確にする
納品物と納期についての記載にも注意が必要です。営業代行の報酬設定には、成果報酬型と固定報酬型があります。成果報酬型であれば、アポイント獲得数や成約数など目に見える成果で報酬が発生するので、報酬の発生ポイントがわかりやすく、この点でトラブルが発生することは少ないでしょう。
しかし、固定報酬型の場合には明確な成果物が設定しにくいので、依頼はしてみたけれども、営業成果がほとんど上がらなかった、ということになりかねません。
固定報酬型でも営業代行に明確な成果を出してもらうためには、具体的に納品物と納期を具体的に設定するように注意しましょう。固定報酬型の場合の成果物は、架電リスト、業務報告書、商談のために作成したプレゼン資料などでいいでしょう。また、納品物を確認するための検収期間も必ず設定するように注意しましょう。
報酬の支払い方法を明確にする
営業代行の報酬の支払い方法についての契約書への記載も明確にするように注意しましょう。営業代行の報酬の支払い方法としては、成果報酬型と固定報酬型、それから一定の固定報酬に成果に応じたインセンティブを上乗せする複合型の3種類があります。
成果報酬型と固定報酬型は、報酬の金額と発生するタイミングがわかりやすいので、特に問題は発生しにくいでしょう。成果報酬型はあらかじめ定めた成果が出た時点で報酬が発生します。固定報酬型は、毎月一定の金額を営業代行会社へ支払います。
特に注意が必要なのは複合型です。固定報酬とインセンティブを契約書に明確に記載しないと、営業代行のスタッフとしては頑張ったはずなのにインセンティブが全く付いていない、と訴えられてしまう可能性が出てしまいます。
複合型の場合には、固定報酬とインセンティブの内容と金額は明確に記載するように注意しましょう。インセンティブが発生する条件と金額を記載した上で、「固定報酬の金額+インセンティブ報酬」と明記すれば大丈夫です。
営業代行の契約書は目的に合わせて用意しよう!
営業代行を依頼すると、営業スタッフを高額な報酬で正社員として雇用しなくてすみます。起業したてのスタートアップ企業や、土地勘のない場所で新規の営業を開拓したいときには、営業代行で優秀な営業スタッフに営業を掛けてもらえるのは、業績をより早く上げるためにも大切なことです。
しかし、営業代行では契約書の記載によって何かとトラブルが発生しやすいのも事実です。営業代行の契約書に記載する内容は、営業代行を利用する目的などによって変わってくるでしょう。
のちのち、営業代行会社や営業スタッフとトラブルにならないように、営業代行の契約書の種類を間違えないようにして、記載内容にも十分な注意をはらいましょう。
>>【無料】営業代行サービスの比較検討をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
決裁者アポ獲得するならアポレル
アポイントの獲得、特に決裁者アポイントの獲得を重要視するなら、ぜひアポレルにお問い合わせください。
アポレルが選ばれる理由を5つご紹介します。
アポレルが選ばれる理由
- 審査制で決裁者のみが登録
- 決裁者へのダイレクトメッセージ機能搭載
- 決裁者限定のオンラインピッチイベントを開催
- アポレルコンシェルジュの仲介サポート
- 完全オンライン完結
アポレルは完全審査制で決裁者のみが利用できるサービスであるため、無駄な時間をかけずに営業活動を実施できます。
また、直接のダイレクトメッセージだけでなく、オンラインピッチイベントやアポレルコンシェルジュの仲介も利用可能です。
完全オンラインで利用できますので、コロナの状況下でも営業機会を逃しません
>>【無料】アポレルの詳細はこちら