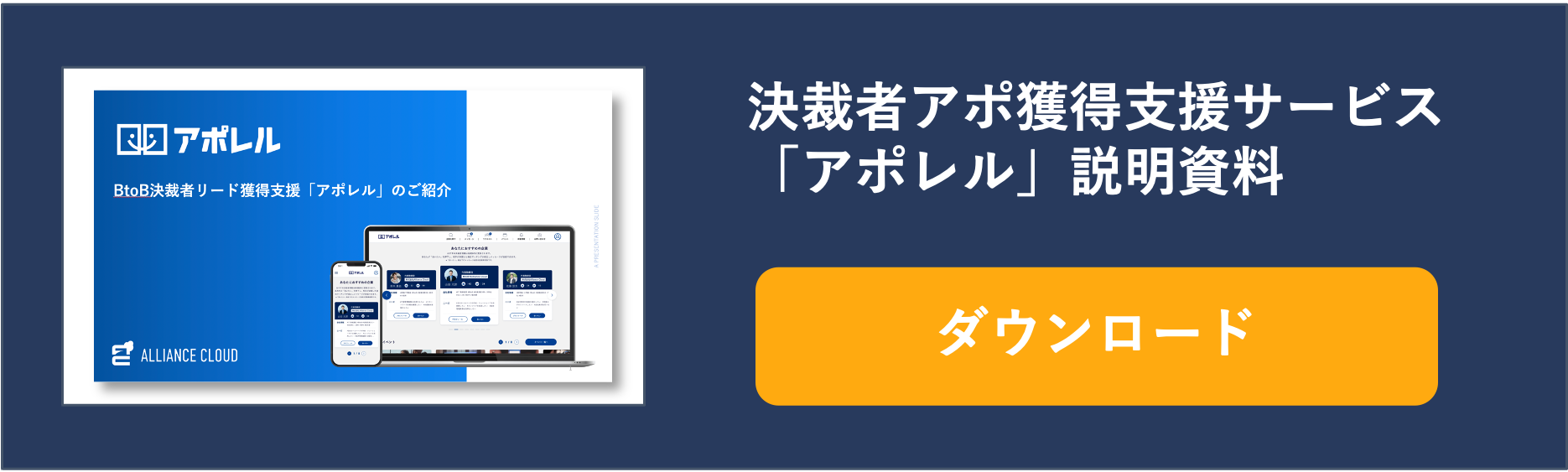小林 広治 (こばやし・こうじ)
株式会社キズナキャスト 代表取締役
1972年長野県諏訪に生まれる。高校卒業後に上京し、早稲田大学理工学部機械工学科に入学。1996年に卒業後、1999年26歳で起業し、株式会社キズナキャストを設立。今年創業23期目に突入。

コロナウイルスの影響で、リモートワークは今や当たり前になりつつあります。そんな中、リモートワークを10年以上前から取り入れ、社員一人ひとりが自分で考えて自分で行動することを重要視し、人の可能性を信じて意志ある人生を応援し続ける会社が株式会社キズナキャストです。今回は、個性を持った社員がたくさん集まる株式会社キズナキャスト代表取締役社長の小林様にお話を伺いました。
マーケティングからシステム開発まで
--本日はよろしくお願いします。早速ですが、小林さんが起業されたきっかけをお聞かせください。
1972年長野県諏訪に生まれ、高校卒業後に上京し、一浪で早稲田大学理工学部機械工学科に入学しました。1996年に卒業後は25歳で創業し、1999年26歳で独立起業、27歳で法人化しました。今年創業23期目に入っています。
はじめはSIerと呼ばれる企業のIT支援部門といった形で会社を立ち上げました。当時は人脈も資金もなかったため、個人向けにパソコンサポートを行っていたのです。個人相手にお仕事をしつつ、いずれは法人に紹介してもらえたらと考えていたところ、開始して1年程で法人向けのサービスへと切り替えることができました。
創業当初はwebマーケティングやwebキャンペーンが始まったばかりの時代だったので、凸版印刷さん、東急エージェンシーさんなどのwebキャンペーンページの制作から裏側のシステムの開発、事務局周りのシステムの開発・運用まで行わせていただきました。
ITは請負で行っていたのですが、ツールとしてのインパクトがあると感じており、ゆくゆくは自社サービスで何か提供できないか考えていました。同時に、2005年のとある出会いによって、ITテクノロジーを屋外広告やポスター・看板に活かせないかと構想を練っていたのです。
現在はデジタルサイネージとして言葉が定着しましたが、当時はまだ言葉としても定着していなかったので、高い可能性を秘めていると感じ、地球上のすべての看板をネットワーク化し、ボタンひとつで変えられるようにしたいと考えました。
その後、2008年のリーマンショック以降は、コンサルティング事業に転身しました。マーケティング系のコンサルティングを行っていましたが、現在は組織改革をテーマにしたコンサルティングを行っています。
ウェルビーイング経営を世の中に広げていくことをテーマに、事業を行っております。
--ウェルビーイング経営とはどのようなものなのでしょうか。
直訳すると「良い状態でいること」になりまして、日本語で言うと「幸福感」「幸せ」ということになります。
ハピネスが一時的な幸福感に対し、ウェルビーイングは健康なども含めた幸福感のことを言います。従業員満足度だけでなく健康経営とも結びついた発展形ではないかと考えています。
コーチングで一人ひとりが自分で考えられる社会に変える
--現在コンサルティング事業を中心に事業展開されていると思いますが、改めてご説明をお願い致します。
戦略支援事業、組織革新コンサルティング事業、マーケティング事業/企業研修・セミナー事業、コーチング事業、事業マッチング事業などです。
具体的には研修として知識をインプットさせること、ワークショップを通じて自分たちで考えさせることで自分たちのあり方を引き出させるようなことを行っています。
物事を学び、成長する方法は「ティーチング」と「コーチング」の2つだと思っています。
今まで多くの企業は上司が教えて部下が真似をする、ティーチング型で行ってきました。
物づくりが中心の大量生産社会ではこちらの方法で生産性を上げることができました。しかし、今後はクリエイティブ社会へと移り変わるので、社員一人ひとりが自分の頭で考えられるようにしないといけません。そうなると、引き出すことも必要になってくるので、コーチングスキルが必要になってくると思っています。
私たちの世界でいうと研修がティーチング、ワークショップがコーチングで引き出していく形で行っています。コーチングはグループセッションもあれば1対1のコーチングもあります。
それをお客様の代わりに我々が行うこともありますし、最終的には企業様が自立できるようにサポートしていきたいので、スキルなどをメンバーに落とし込んでいくため、ティーチングからコーチングまで立ち会ってアドバイスするケースもあります。
--サービスを導入いただいているお客様はどのようなジャンルの方が多いのでしょうか。
100人以下の規模の会社様が中心です。最近ですと、50人規模のOA機器の営業会社様の各部署の主要メンバー10人を集めて、研修型のワークショップを行いました。実績で言うと、去年のコロナ禍においても前年比2倍の売り上げを上げることができ、非常に求められているサービスだと感じております。
営業は結果としてわかりやすいところがあるので、お客様の満足度的には出やすいです。弊社が行っているのは組織そのものの変革であるため、前述のOA機器さんの場合ですと、1年目は管理部門のメンバーも入れて研修を行いました。通常ですと、縦割りで横のコミュニケーションがしづらい企業が多いですが、研修を通じて横のコミュニケーションもできるようになり、会社全体の心理的安全性も高まりました。
--貴社の独自性や強みについてお伺いできますでしょうか。
最初の面接からずっとオンラインで対応しています。コロナ禍でリモートワークが推奨されていますが、弊社では10年以上前からフルリモートで行っておりますので、社員各自が自分で考えて自分で動けるようになっています。考えさせる支援の仕方に独自性があるのではないかと考えます。
ウェルビーイングマネジメントを日本に浸透させる
--今後の中長期的な事業展望についてお伺いできますか。
「幸せ」を企業経営の中心軸にすえたマネジメントスタイルの「ウェルビーイングマネジメント」を日本の社会に浸透させたいと考えています。新型コロナウイルスが収束してリモートワークの必要性は少なくなる可能性もありますが、リモートワークそのものは継続すると思っています。
日経新聞の企業アンケートでも、8割の企業がリモート継続と話していました。理由は働き手側が家で働くことの心地よさに気が付いたからではないかと思います。
子育て世代ですと、子供の成長を見ることもできますし、子供にも背中を見せられるので良いと思っています。これがまさにウェルビーイングだと思います。
喜びを感じることで仕事に打ち込めてやる気も増して生産性もアップすると思います。
子どもが仕事の邪魔をするという問題もありますが、それが当たり前の社会になるほうが健全じゃないかと考えています。
まずは大企業が導入して成功事例を出していかないと、中小企業はなかなか踏み込めないと思っています。成功事例をベースにして、もっと多くの中小企業の変革に力をいれていきたいです。
--ありがとうございます。最後にProfessional Onlineを見ていただいている経営者、決裁者の方に向けてメッセージをいただけますか?
時代の変化の本質を経営者の皆様には捉えていただきたいと思っています。コロナが引き起こした変化ではなく、元から起きていた変化がコロナによって加速しただけだと思っています。
大量生産の社会からクリエイティブな社会に変わってきています。社員やメンバーが自分で考えてアウトプットする世の中に変わってきていますし、それができる会社だけが生き残れると思っています。社員の頭を使わせていくことが必要になってきています。
経営者はそこをしっかりと見ていかなくてはならず、働くことに喜びを感じることで自然と業績が伸びてくるようになるはずです。社員の幸せを真剣に考える時代なので、経営者自身がまずはウェルビーイング(幸せ)になってほしいなと思います。
--本日はどうもありがとうございました。
株式会社キズナキャスト
Professional Onlineでは無料で経営者インタビューに掲載いただける方を募集しています。
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
プロフィール

小林 広治
会社情報


決裁者アポ獲得支援サービス「アポレル」に登録すると、日替わりでレコメンドされる著名な経営者と出会うことができます