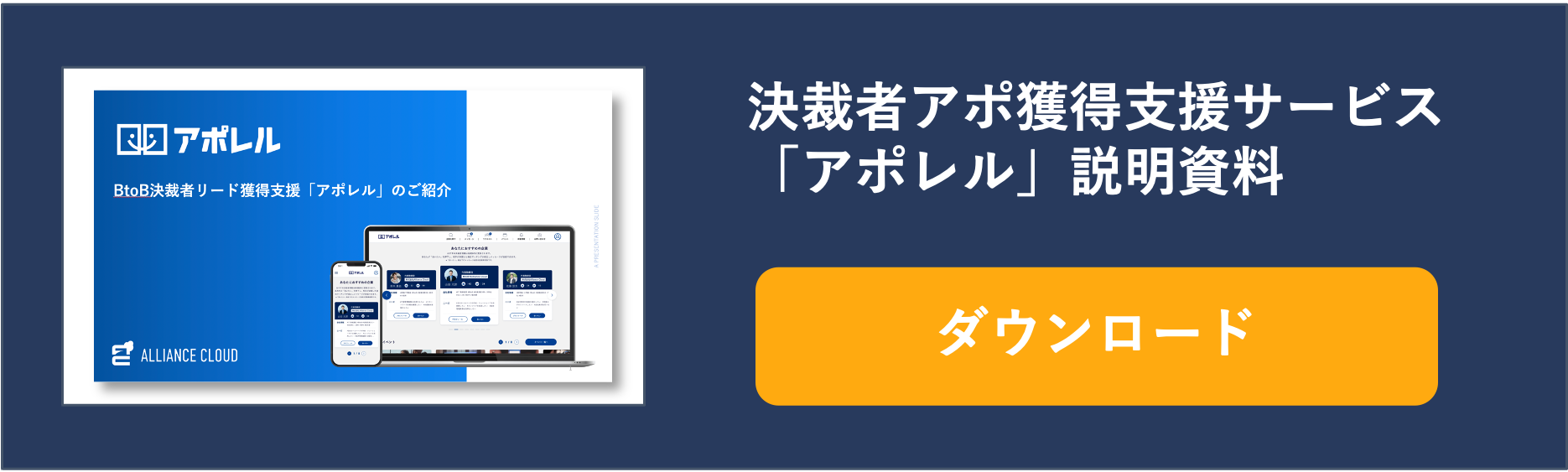原 英洋(はら・ひでひろ)
株式会社ふらここ 代表取締役
1963年生まれ。祖父は人間国宝の人形師、原米洲さん、母は女流人形師の原孝洲さん。慶応義塾大経済学部を卒業後、出版社に勤務。1987年1月、実家の「五色株式会社」に入社。同年3月に父が他界し、専務取締役として経営に関わる。2008年に独立し、「ふらここ」を創業。売上高は前年比120%以上の成長を続けている。

ひな祭りや端午の節句は日本を代表する文化です。しかし、少子化やライフスタイルが変化するなか、人形を飾る機会は年々少なくなっています。そんな中で、新しい時代の嗜好や生活に合ったひな人形や五月人形を製造・販売する株式会社ふらここの原英洋代表取締役にお話を伺いました。
伝統文化の後継者として
--本日はよろしくお願いします。早速ですが、原さんが起業されたきっかけをお聞かせください。
私は代々人形師の家系に生まれて、跡取りではあったのですが、人形師になるつもりはありませんでした。実は物書きになりたいという志があり、大学卒業後は出版社に入社したのです。しかし、その二年後に父が急に体を壊して他界してしまい、家業を手伝うことになりました。そこで後継者として経営に携わっていたのですが、実際に店頭などでお客様と話をしていく中で、昔ながらの人形がお客様に飽きられているといった、市場の変化を実感することになりました。
また、これまでであれば、お祖父様やお祖母様が孫が生まれたときに人形を選び、それをプレゼントするという形だったものが、子どもが生まれると若いお母さまがご購入されるといった形で購買行動も変化していました。
そういった状況で、今までと同じ人形を作っていたのではだめだと感じ、職人さんに新しい人形作りを提案したのですが、当時は昔ながらの職人さんがものづくりの中心を占めていて、なかなか私のような若い人間の意見が通らない状況でした。
そこで、自分の目指す人形作りをやりたいということを母にも伝え、了承を得たうえで独立し、現在の会社を設立しました。
時代に即した新しい文化を提供する
--現在の事業展開や手掛けている新事業について、改めてご説明をお願い致します。
私どもの会社では、ひな人形、五月人形の製造販売を行っています。販売形態はほぼ100%ネット通販で、今ではある程度認知をいただいて、創業以来業績も伸び続けております。
--貴社の独自性や強みについてお伺いできますでしょうか。
昔ながらの人形といいますと、伝統に培われてきたもので、細面の目鼻立ちのはっきりしたうりざね顔、公家顔というものが中心でした。また、飾ると部屋の一角を占めてしまうという大きな飾りが一般的です。
しかし私どもの人形は、顔立ちはかわいらしい赤ちゃん顔をしています。また、大型ではなく幼稚園の女の子の手のひらに載ってしまうコンパクトなものです。色も、伝統的な手法で作ってはいますが、従来の落ち着いたシックな色合いとは一線を画し、明るいパステル調の衣装が特徴になっています。これはお人形を購入する、若いお母さまの嗜好を反映したものです。
当初、こういった人形を作ってはどうかと提案したとき、職人さんたちには「おもちゃみたいだ」と言われて反対されましたが、実際に販売してみるとお客様のご好評をいただいて、初年度から完売、今まで業績を伸ばしてくることができました。
--伝統産業に関わる職人さんをどのように説得したのでしょうか。
日本のひな祭りに関しては約1000年、端午の節句に関しては約1250年の歴史を持つ文化です。そういった古くから培われてきたものを変えるということに関しては、非常に強い反対を受けました。
しかし考えてみれば、人形文化も1000年の歴史の中でずっと同じものが守り続けられてきたかというと、そんなことはありません。丹念に歴史を調べていくと、人形の形、文化、風習は時代によって大きく変わっている。逆に言えば、変わったからこそ受け継がれてきたということもできます。
伝統文化でいうと、歌舞伎もそうですね。歌舞伎は江戸時代から始まっていますが、始まったときはまったく新しいもの、現代でいうジャニーズのようなものだったかもしれません。それが続く中で伝統文化になったわけです。歌舞伎には昔からの演目もありますが、それだけやっているわけではなく、時代に合わせて変えていく部分も多いですし、常に新しいものを取り入れています。
古いものを守るだけではやがて博物館に入って終わってしまう。それを続けていくためには、その時代に生きる人たちの好みに合わせて変えていく必要があります。
伝統文化の職人さんの世界では、古いものを守るという意識がとても強く、変えたがらないという現状がありますが、まず最初は熱意を込めて説得するしかありません。わかってくれる人は少なかったのですが、実際に作って販売し売れていく光景を見せることで変わっていきました。
やはり、職人さんにしてみれば自分が作ったものが売れるというのはうれしいものです。それが毎年続くと、うれしいのはもちろん、同時に収入も増えていきます。現在では、職人さんのほうから「こんなものを作ってみては」という提案が出るようになりました。
日本の人形文化を時代に合わせて表現
--今後の中長期的な事業展望についてお伺いできますか。
この業界は衰退期に入っていて業界全体が年々縮小しています。しかし、競合も新しいものを作り始めていて、これからいい形に変わっていけばいいと思っています。
少子化ともいわれていますが、それでも毎年80万人が生まれています。将来的に50万人まで減少するという予想もありますが、それでもまだ50万人です。人形業界が全体でも毎年50万セットを作っていることはなく、せいぜい20万セット程度でしょう。つまり、まだあり余る市場があるということになります。
日本に暮らす人の中で、ひな祭りや端午の節句を知らない人はいないと思います。また、世界中に人形の文化はありますが、それは手に取って遊ぶおもちゃとしての人形や、祈祷のための道具で、観賞用として人形を極めた日本文化は世界の中でも非常にまれで、誇るべきものです。言い換えれば、ひな人形や五月人形に限らず、日本人は人形になじみがあり、愛着を持っている人も多い。それをいろいろな形で表現し、現代に合わせた形で広めていきたいというのが今後の目標です。
--最後にProfessional Onlineを見ていただいている経営者、決裁者の方に向けてメッセージをいただけますか?
伝統産業であれ、そのほかの業界であれ、常に変化する市場を敏感にとらえて、対応し続けていくことが大切だと思っています。伝統産業の方と話をしていると、どうしても守りの話をされる方が多いのですが、伝統産業といえど、常に変わっていかなければ市場に置いてきぼりを食ってしまうし、お客様からも見放されてしまう。常に変化に対処していくことが大切ではないかと思います。
--本日はありがとうございました。
株式会社ふらここ
Professional Onlineでは無料で経営者インタビューに掲載いただける方を募集しています。
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
プロフィール

原 英洋
会社情報

決裁者アポ獲得支援サービス「アポレル」に登録すると、日替わりでレコメンドされる著名な経営者と出会うことができます