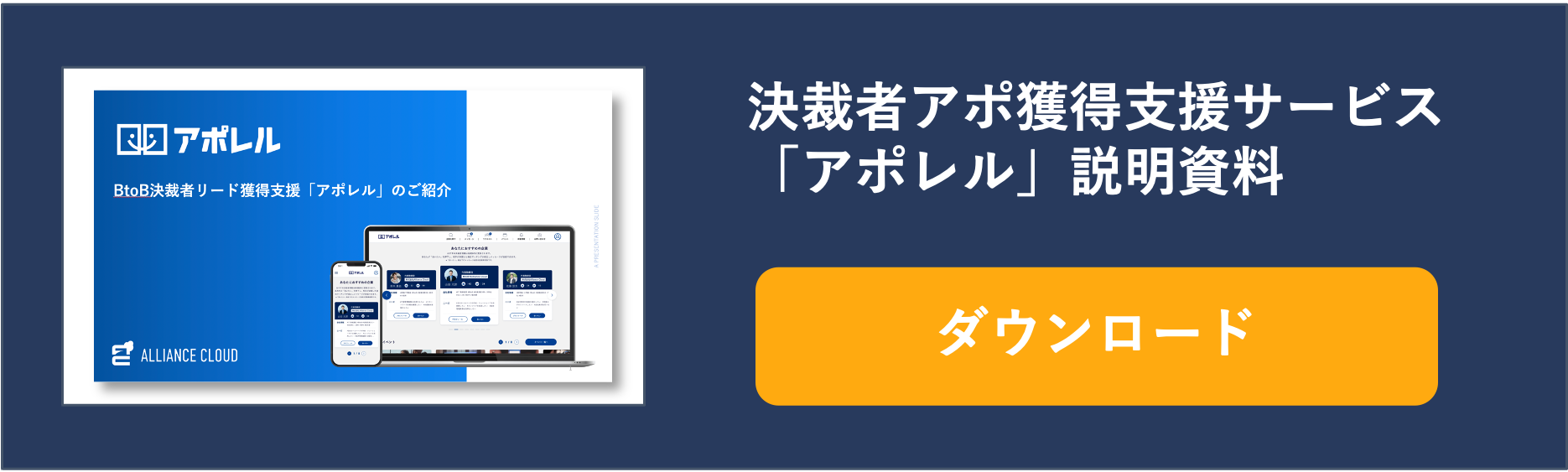飯田 佳明(いいだ・よしあき)
株式会社Engineerforce 代表取締役
1991年生まれ、福岡県福岡市出身。成蹊大学経済学部を卒業後、富士ソフト株式会社へ新卒で入社。その後、フィンランド企業のThe Qt Companyの日本オフィスへ転職。両企業でのを経験をもとに、AIを活用したITエンジニア向けの見積り作成ナレッジシェアツール「Engineerforce(エンジニアフォース)」を考案。2020年8月に株式会社Engineerforceを設立する。アイディアが株式会社経済界主催の「金の卵発掘プロジェクト2020」審査員特別賞を受賞。

エンジニアの仕事は激務というイメージをお持ちの方は多くいらっしゃるかと思います。そのイメージ通り、エンジニアは多忙な日々を過ごしていると仰るのは、株式会社Engineerforce代表取締役の飯田様です。自身もSIer事業を経験し、エンジニアの見積り工数や業務内容に違和感を感じてきました。IT化により増え続ける業務や課題をエンジニア目線で解決するツール「Engineerforce」が誕生したきっかけや、今後の事業展望をお伺いしました。
全エンジニアの永遠の課題を解決する使命をもって会社を設立

--本日はよろしくお願いします。早速ですが、飯田さんが起業されたきっかけをお聞かせください。
大学卒業後は富士ソフト株式会社へ入社し、受託開発や自社プロダクト開発に6年間ほど従事しました。退職後は、フィンランドの企業でソフトウェア開発などを行っているThe Qt Companyの日本オフィスへ転職。自社プロダクトの拡販に携わりました。外資系企業も経験したからこそ日本企業との文化の違いを身をもって感じましたが、見積り工数の部分に関しては業界共通の課題でした。
その理由は、エンジニアがExcelをつかって工数計算をしていたり、担当者の経験ベースで工数が変わってしまうことにありました。見積りを正確に、かつ簡素化するアイデアを考案し、2020年8月に株式会社Engineerforce(エンジニアフォース)を設立。ITエンジニアに特化したナレッジシェアツール「Engineerforce」をリリースしました。
--1期目を終えた現在の心境はいかがでしょうか?
当初の計画通りに進んだこともあれば、改善が必要なこともありました。サービス立ち上げの難しさを痛感した1年でしたね。
当初のコンセプトはAIと人間でのダブルチェックでしたが、実際にクライアント様に使用していただくと、AIの信憑性に疑問を抱く声をいただきました。また、見積りを作成する上で肌感覚も必要な要素だと思うのですが、AIにはそれができません。
この課題を改善したのが、過去のデータを一元化して管理する機能です。当初のAIの機能は残しつつ、他の人が作った見積りや実績時間を参照することができるようにしました。この機能によって、簡単かつ正確に見積りを作成することが可能になりました。現在の形になるまで少々遠回りをしてしまったように感じますが、今後もよりよいサービスにするため改善できることをしていきたいです。
嬉しい誤算としては、1年で250ほどの企業に導入していただいたことです。自社で営業も行っていますが、お問い合わせから導入につながった例が圧倒的に多く、社員全員で喜びを噛みしめました。しかし、この結果に満足せず、2年目以降も地に足をつけて事業を展開していきたいです。
ITエンジニアの業務こそDX化し、速く・正確にこなす
--現在の事業内容を改めてご説明お願いいたします。
見積り工数のナレッジシェアツール「Engineerforce(エンジニアフォース)」の開発、販売をメイン事業としています。「Engineerforce」は、ITエンジニアに特化した見積もり支援システムであり、より正確に、かつ簡単に見積りを作るためのツールです。
また、タスクを登録することで過去の見積りを流用したり、チーム内で情報をナレッジシェアしたりすることも可能です。過去のデータはすべて履歴として残すことができるため、サーバー上でエクセルを探し回り、時間を無駄に消費することがなくなります。オンライン上で見積書の作成から受発注、請求書発行、検収処理まですべて完結することができ、作業の負担を格段に減らすことも可能です。
料金形態は月額制で、その他に初期費用がかかります。トライアル版があり、実際に使用し納得していただいてから契約に至っているため、解約率は低いです。採用していただいている企業は、大企業、中小企業、零細企業まで偏りはありません。企業規模に関わらず、SIer事業の分野をターゲットとしています。
--貴社の独自性や強みについてお伺いできますでしょうか。
創業者の私だけでなく、弊社のメンバー全員がSIer事業を経験していることが強みです。業界の改善すべきことをメンバーが共有していることで、弊社が向かう方向に社員全員で進んでいくことができます。Founder/Market Fit(創業者とマーケットの適合性)は高いと自負しています。また、クライアント様とも同じ目線でやり取りすることができますので、悩みや課題も共有しやすいのも特徴ですね。
--貴社サービスを有効に活用されている事例があれば教えてください。
「Engineerforce」を活用している企業様からは、エンジニアだけではなく、営業職の方もより一層効率が上がったと伺っています。特に営業職の方は、お客さまの開発にどれぐらいのタスクや工数が必要なのか把握していないことが多いように感じています。そのため、お客さまからの質問や要望を毎回持ち帰り、エンジニアに確認をしてから再度提案するパターンに陥ります。この段階を踏むことで、コミュニケーションコストが高くなってしまったり、お客さまの熱量が下がってしまったりするケースが往々にしてあるのです。この課題を「Engineerforce」でクリアにし、商談中に最適な提案をすることで受注確度が高まっていると喜びの声をいただいています。
社名にもある通り、エンジニアが仕事をしやすくなるよう有益な製品を生み出していくことが弊社のビジョンです。この想いを忘れることなく、クライアント様の声を聞き、よりよい商品にしていくことでエンジニアの業務を改善していきたいと考えています。
上場を目指し、さらにエンジニアに貢献する企業になる

--今後の中長期的な事業展望についてお伺いできますか。
今後も事業を継続発展させていくために上場を目指しています。弊社が上場することで弊社のサービスを通し、エンジニア業界をますます発展させていくことができると思っています。上場を目指す第一歩として、先日ベンチャーキャピタル2社からの出資が決まりました。創業期に2社からも出資があったことに驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。弊社のサービスを使用したことで残業が減ったとエンジニアの方々に言ってもらえるよう、良いサービス作りに日々まい進していきたいと考えています。
また、現在の課題は知名度が低いことです。今後さらに知名度を上げるため、マーケティングにも注力していきたいです。さらに、効率よく営業し、契約を獲得していくために商社や営業のアウトソーシングも検討したいと考えています。
--最後にProfessional Onlineを見ていただいている経営者、決裁者の方に向けてメッセージをいただけますか?
ITエンジニアの流動性は年々高まり、従来の属人的な見積り手法では、見落としがミスに繋がったり、業務が増加する一方だったりします。また、せっかくのナレッジも社内に貯まっていかず、成功例も活用されにくいケースがあります。
これらの課題を解決し、エンジニアの業務改革をしたいとお考えの企業様は、まずは「Engineerforce」のトライアル版をお試しください。根本的な仕組みの部分から改善することができます。興味をお持ちでしたらお気軽にお問い合わせください。
–本日はどうもありがとうございました。
株式会社Engineerforce
Professional Onlineでは無料で経営者インタビューに掲載いただける方を募集しています。
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
プロフィール

飯田 佳明
会社情報


決裁者アポ獲得支援サービス「アポレル」に登録すると、日替わりでレコメンドされる著名な経営者と出会うことができます