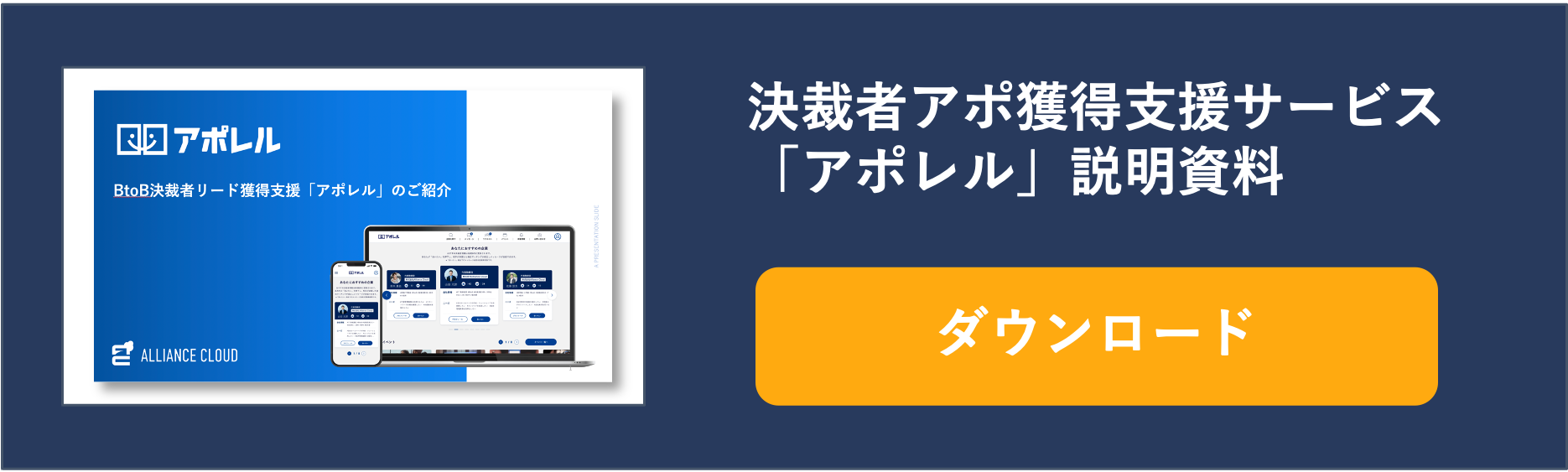藤田英明(ふじた・ひであき)
株式会社アニスピホールディングス 代表取締役
1975年東京都出身。明治学院大学社会学部社会福祉学科卒。在学時から社会福祉法人で高齢者介護に携わり、2003年に日本初の混合介護を提供する夜間対応型高齢者デイサービス(現在の「茶話本舗」の原型)を立ち上げる。2016年に株式会社アニスピホールディングス設立。内閣府規制改革会議参画の経験も持つ。
著書に『図解でわかる介護保険ガイド』『社会保障大国日本』『介護再編』。メディア出演多数。

急速な高齢化社会の進行により増え続ける社会保障費。有効に使うため、障がい者福祉の分野においては、障がい者自らが自立した生活が送れる環境や支援策の整備が急がれています。
福祉領域を「競争の無い世界」と言い切り、これまで拾われていなかった利用者ニーズを取り入れる形で次々に新しいサービスを生み出している株式会社アニスピホールディングスの藤田様にお話を伺いました。
福祉の現場をユニークなアイデアで改善

--本日はよろしくお願いします。早速ですが、藤田さんが起業されたきっかけをお聞かせください。
大学で社会福祉を専攻し、在学中から高齢者介護施設の相談員として社会福祉法人に勤務していました。そこで10年ほど経験を積んだのち、2003年に夜間対応型のデイサービス(保険内と保険外を組み合わせた日本で初めての「混合介護」サービス)を行う施設を埼玉県で起業し、フランチャイズで全国950カ所に展開するに至りました。中国・韓国・台湾にも施設があります。
2015年にその事業は後進に託し、新たに株式会社アニスピホールディングスを設立しました。弊社ではペット共生型障がい者グループホームや、運動療法を取り入れた障がい者向けデイサービスを提供しております。これらのビジネスアイデアは自分の体験が元になっています。
子どもの頃、猫が好きでケガをした猫を見つけては勝手に保護していました。現在、日本では年間3万頭以上の犬猫が殺処分されているのですが、福祉と保護犬・保護猫を掛け合わせれば、殺処分される命を継続的に救える仕組みが作れるのではないかと考えました。
また、運動療法型のデイサービスを提供しているのは、学生時代に全国大会に出場するほど自分がサッカーに打ち込んでいた経験から、運動することの良さを実感していたためです。うつ病など精神障害のある方や知的障害を持つ方に対して、運動療法の治療効果があることは明らかになっています。しかし、本人たちは経済的な事情もあり、ジムに通って運動をする機会が少ないという実情があったことから、サービスの構築に至りました。
利用者のQOLを向上させ、社会問題も解決できるビジネス
--ご自身の体験と社会問題が組み合わさり、現在のサービスにつながったのですね。まず、障がい者デイサービス「ワーカウト」についてご説明いただけますか。
このサービスは、フィットネスをデイサービスに取り入れ、利用者の頭と身体に刺激を与え、心身をリフレッシュさせることを目的としています。
障がい者デイサービス自体は全国に6,000カ所ありますが、運動の機会を提供している施設はほぼありません。しかし、利用者の視点で考えれば、一日中することがなく事業所にいるだけというのはつまらないと思います。また、精神障害の薬を飲んでいると副作用で太りやすくもなってしまいます。肉体面・メンタル面の改善をするという点でも運動は必要なのです。
たとえば、精神障害の人は歩けないと思い込んだら、実際の歩行機能の有無に関わらず、一生歩けないと思ってしまいます。弊社では、プロのK-1格闘家とキックボクシングを行うプログラムがあるのですが、自分が立てないと思いこんでいた利用者がプログラムに取り組むうちに、立てるようになって驚いたという話もありました。
また、身体が健康になると精神的にも良い影響があります。利用者のご家族からいただいた話では、施設で運動をするようになってから、ご家庭での暴力行為が改善した方もいるそうです。
現在はデイサービスが11カ所あり、2021年11月には3カ所を増設予定です。2022年度には100カ所を目指しています。
--ペット共生型障害者グループホーム「わおん・にゃおん」についても教えてください。
障害者グループホームとは、障がいを持つ方が4人ほどで、生活や健康管理といった支援を受けながら共同生活を送る住宅のことです。
このビジネスでは、保護犬・保護猫を事業所で保護し、殺処分される命を1つでも減らすこと、アニマルセラピー効果によってグループホーム入居者の生活の質(QOL)を向上させることを同時に狙っています。すでに全国で770拠点を超える事業所がありますが、さまざまな理由から今後はさらに必要になるビジネスだと考えています。
まず、1つ目の理由として日本の人口構造的に、障害者グループホームは今後さらに数を増やす必要があります。現在、日本の65歳以上の高齢化率は28%ですが、2045年頃には45%に達するとも言われています。自分たちで障がいのある子どもの面倒を見ていた親も歳をとるため、代わりに子どもの面倒を見てくれるところを探すことになるでしょう。
また、高齢者介護施設は8種類ほどありますが、障がい者施設は施設入所とグループホームの2種類しかありません。施設入所においては重度の障がいを持つ方しか受け入れができないルールがありますので、必然的にグループホームの入居者が増えることになります。
2つ目は、財務省の政策です。国の収入と支出をイコールにすることを目指していますが、55兆円強の税収に対して医療費などの社会保障関係費は年間40兆円弱。支出で一番大きな割合を占めています。だからこそ、入院をしている人を病院から出すという政策をしているのです。しかし、一人暮らしもできない、実家にも帰れない障がい者はどうしたらいいのでしょう?その人たちの受け皿として、障がい者グループホームが必要になります。
3つ目は空き家の開発や再利用提案という視点です。自宅や使っていない空き家を障がい者グループホームにし、社会貢献型不動産として有効活用できるような仕組みを提供しています。
日本には現在800万戸の空き家がありますが、2047年には2,100万戸まで増えると予想されています。空き家の活用というと、古民家カフェなどに転換する方法はよく聞きますが、もっと多くの空き家が活用できる方法を考えるなら、家としてそのまま使えるグループホームが最適です。
最後に、犬猫の殺処分の問題です。この40年で50分の1に減ったとはいえ、行政に殺処分される数は年間3万頭を超えます。今は動物保護団体が引き取ってなんとか殺処分を免れている状態ですが、寄付金で成り立っている団体のため、寄付金が集まらないと倒産する可能性があります。
保護猫カフェの中には、コロナ禍でお客さんの来店が激減し経営が困難なところもあります。そうなると、せっかく保護した猫たちは行き場がなくなってしまうのです。一カ所でたくさんの猫を保護することほどリスクのあることはありません。弊社のサービスモデルでは、グループホームごとに犬や猫を1〜2匹連れていきますが、万が一ホームが1か所無くなってしまっても次に行く先は見つけられます。
なにより、入居者にとってもアニマルセラピー効果があり、ニーズがあります。また、動物は世話がいるし、犬の場合は散歩も必要です。自分が世話をしてあげないといけないという責任感が入居者に生まれ、良い影響を与えてくれます。
開始当初こそうまくいくか不安はありましたが、弊社のグループホームには動物好きな人が入居してくるようになりました。利用対象者のセグメント分けができ、他の施設との差別化にもつながっています。
現在は、775拠点にフランチャイズで導入しており、今後は8,000カ所まで増設を目指しています。人間の福祉を向上させていくのは当然として、日本で非常に遅れている動物福祉を向上させていくために運営をしています。
障がい者の一生を総合力とテクノロジーで支える

--ユニークなだけでなく、たくさんの社会問題を解決できるビジネスだと感じました。では、貴社の独自性や強みについてお伺いできますでしょうか。
弊社には、障がい者グループホーム、訪問看護、相談支援事業所、生活介護があります。12月には、新たに障がい児向けのサービスをオープンする予定で、単体ではなく複合化できるのが一番の強みです。
たとえば、グループホームの近くにデイサービスや訪問看護の拠点を作ると売上が倍増します。利用者利便の観点だけでなく、経営面でも強みになっています。
また、最近話題のSDGsの観点からも多岐にわたる領域をカバーしています。貧困・人権・公正な社会はもちろん、空き家を利用することで環境面にも貢献できていると思います。
独自性の面では、福祉の現場にテクノロジーを積極的に取り入れています。人にしかできない部分だけを人が受け持つという形にしていきたいです。未だにファックスと印鑑が多い業界ですが、弊社ではカメラを利用して食事記録をしたり、声で精神状態が分析されるシステムを導入して自動化を進めています。
--今後の中長期的な事業展望についてお伺いできますか。
できるだけサービスを複合化し、子どもが生まれて一生を終えるまで一気通貫で見られる状態を目指しています。その中で、障がい者の働く場所も作っていきます。
現在の障がい者の平均賃金はひと月に1万5千円です。最低でも10倍の15万円や20万円もらえて、障がい者でもある程度稼げるようにしていきたいです。また、入居者が高齢化して亡くなる時までを見届けるためには、看護や医療の充実も必要です。
もう一つは、テクノロジーの利用です。データの蓄積、カメラの設置をすすめ、撮りためた動画をAIを使い行動パターン解析します。声のトーンや顔の表情から、利用者のケアの仕方や、職員の管理に役立てようとしています。
自社開発は難しい分野ですので、既存のシステムを利用したり、アライアンスを組んで行っていくつもりです。特に、画像認識や人工知能に強い会社を探しています。顔認証で離れた位置からでも個人を特定できる認識力のあるものや、音声や画像の表情から精神状態を解析してくれるものが欲しいですね。
福祉事業は税金や保険料で成り立っているため、無駄に給付金が支払われていないか精査が必要です。本当に効果的なお金の使い方をしている事業所だけが残るような制度設計にすれば、無駄な社会保障費は削減できるはずです。そのために国への提言は続けていきます。
--最後にProfessional Onlineを見ていただいている経営者、決裁者の方に向けてメッセージをいただけますか?
コロナ禍で経営環境が変わり、良い影響、悪い影響を受けた会社があると思います。その点、福祉業界は安定して利益を上げられるため、事業領域のひとつとして持っておくと、環境変化によって本業が赤字になったときにも、福祉事業で補填して黒字にできるというリスクヘッジにもなります。個人法人問わず、弊社事業へのご参加をぜひご検討ください。
--本日はどうもありがとうございました。
株式会社アニスピホールディングス
Professional Onlineでは無料で経営者インタビューに掲載いただける方を募集しています。
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
プロフィール

藤田 英明
会社情報


決裁者アポ獲得支援サービス「アポレル」に登録すると、日替わりでレコメンドされる著名な経営者と出会うことができます